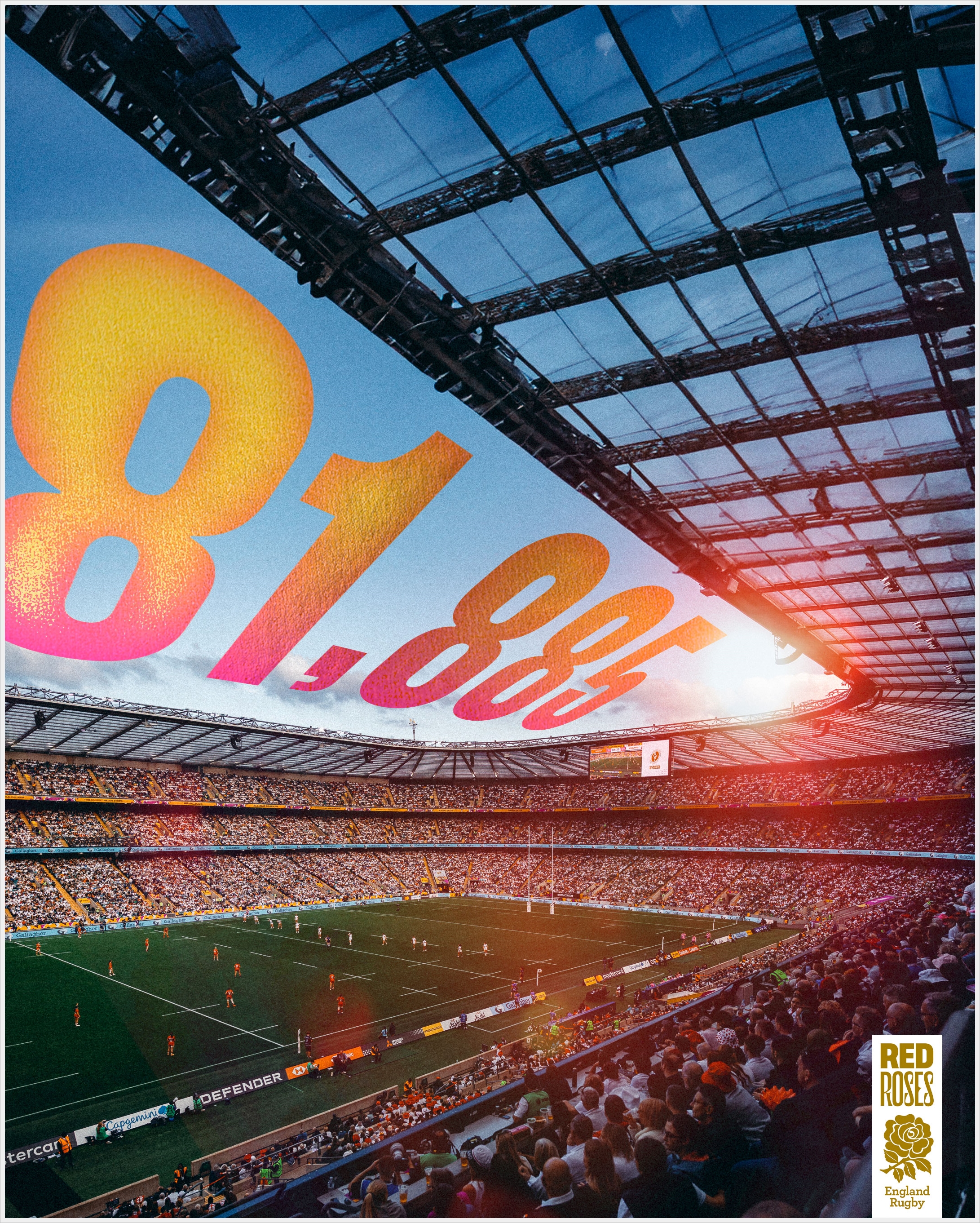644 桐蔭学園、強さの秘訣
2025年1月7日
全国高校ラグビー決勝が行われ、桐蔭学園が京都成章を 36 - 15 で下し、3大会連続6度目の優勝を果たしました。3連覇は史上6校目の快挙です。今大会では常翔学園、東海大大阪仰星、大阪桐蔭と、史上初めて1大会で大阪勢3校撃破の偉業も達成しました。
先日の大阪桐蔭との準決勝の後、
藤原監督の著書
を読み直してみました。桐蔭学園が全国大会で優勝・連覇する強さには、いくつもの明確な要素があると感じましたので、あくまでも個人的な見解ですが、以下に整理してみましたので、もしご興味あればご覧ください。
-----
1. 選手主体のチーム文化
桐蔭学園は監督・コーチが選手に指示を与えるだけで終わらず、選手自ら考え、話し合い、判断する習慣を大切にしています。若手でも意見を出し合い、作戦を自分たちで組み立てることで、試合での応用力・判断力が高まっています。
2. 変わらない基礎と継続した取り組み
指導体制が長く安定しており、監督・コーチ陣が長年同じメンバーで続けていることが強さにつながっています。繰り返し基礎練習を積み重ね、ラグビーの基礎技術を徹底して磨くことで、どんな場面でも安定したプレーができる土台ができています。
3. 冷静で戦術に基づいたプレー
元代表選手のOBが語るように、桐蔭学園は「気合だけ」に頼らず、理性的・戦術的に試合に臨む文化があります。「気合は5分しか持たない」という指導のもと、事前の準備と分析を重視し、試合中も冷静に状況を判断しています。
4. 完成度の高い基礎技術と柔軟な戦術
基礎技術(例えばパス・キャッチなど)を繰り返し鍛えることで、どんな展開でも対応できる力を身につけています。同じラグビーでも年ごとに選手の特性は違うため、戦術を柔軟に変えられるのも強さの理由です。
5. 粘り強さと身体的な強度
準々決勝・準決勝・決勝まで、接戦や苦しい時間帯でも集中力が切れず、後半にギアを上げて逆転する力を発揮しています。これはフィットネスやメンタルの強さの表れとも言えます。
6. 指導者の長期的な育成ビジョン
藤原秀之監督は20年以上桐蔭学園を率い、「常勝軍団」としての文化づくりをしてきました。長い指導経験を通じて選手育成の質が高く、チーム全体の安定感につながっています。
7. まとめ
桐蔭学園の力は単に体力やサイズだけではなく、
・選手自ら考える文化
・基礎技術の徹底
・安定した指導体制
・戦術理解と冷静さ
・粘り強い試合運び
の組み合わせによる総合力です。これは単年の偶然ではなく、長年の積み重ねとチームのDNAとして根付いた強さと言えると思います。
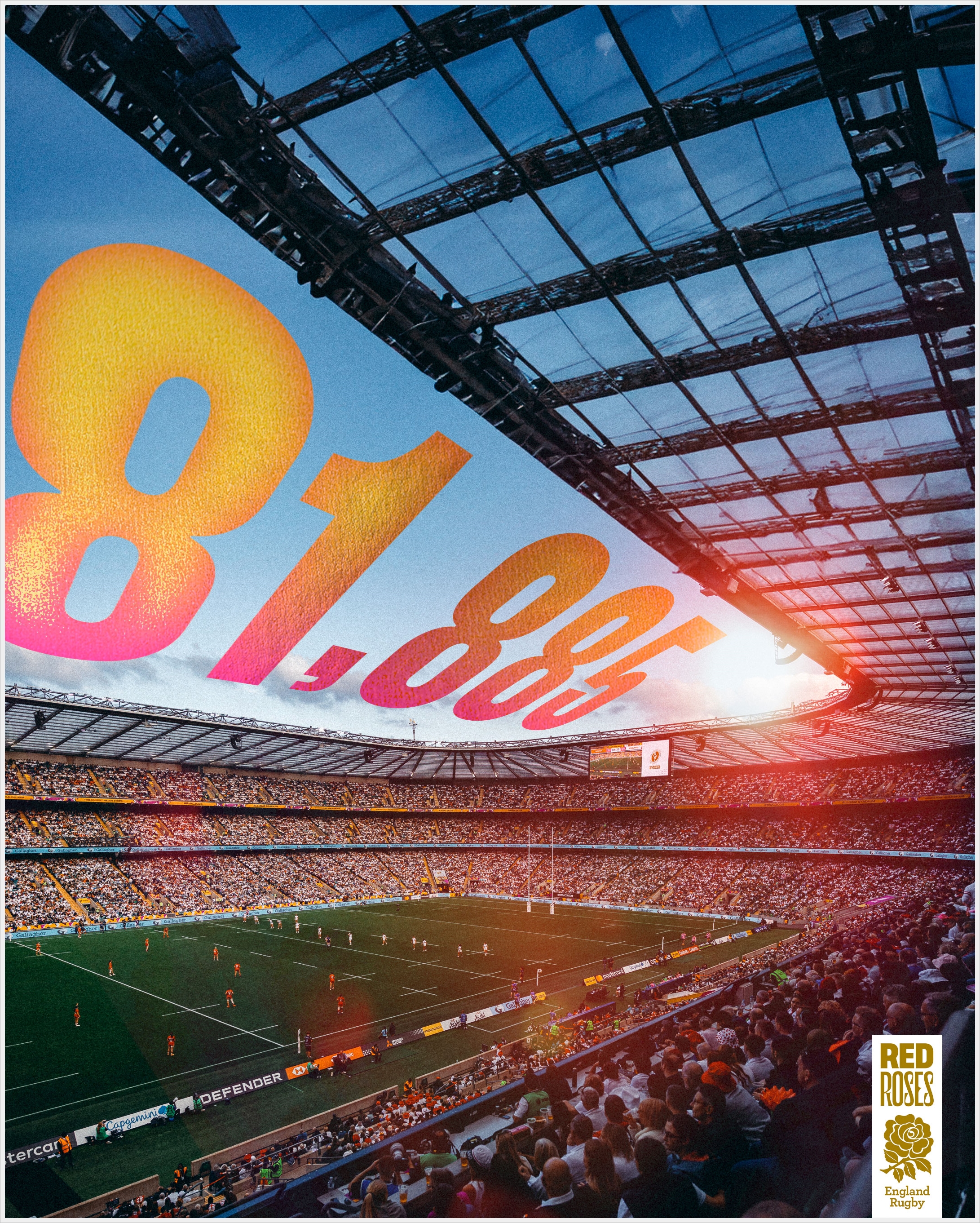


↑